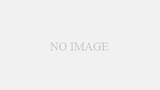居住自治体では、令和7年度から、市内に居住する希望する全世帯等を対象に、防災行政無線・戸別受信機が無償貸出されることから、市役所に設置申請をさせて頂いた。
過日、早々に戸別受信機を自宅に設置を頂いた。
これまで、当方、防災行政無線(同報系)に係る制度化に向けた実証試験、技術的条件等々の検討審議、民間標準化(ARIB標準規格)に係る様々な取組み[1][2]に多々、参画をさせてきたところである。
また、戸別受信機の有用性については、これまで、自営無線通信の一つの重要なシステムである防災行政無線に関わる、言わば、「システム供給ベンター」の立ち位置から、その普及促進が望ましい等々の意見、提言[3]をしてきた経緯にある。
このような中、自宅に設置された戸別受信機に関して、自宅近傍に設置されている屋外拡声子局(屋外スピーカー)からの拡声報知(放送)に比して、その報知情報の「屋内での聴き易さ」を改めて、「地域住民・ユーザ視点」で実感し、その有用性を再確認したところである。
(日々の定時放送=学童下校時地域見守り、夕方のチャイム♪等の聴取実感)
さて、災害発生時等の地域住民への情報伝達体制の強化と、確実に情報を伝達するための手段の多層化・多様化については、これまでその有用性について、多々の行政施策が示され、具体的な整備が進められている。例えば、周知のとおり、総務省消防庁から、「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」(令和7年3月改定)[4]が示されている。
ここでは、防災行政無線についても、取り纏められており、防災行政無線(同報系)における戸別受信機は、例えば、スマートフォンが普及し、ほぼ100%に近い人口エリアカバー率が達成されている現状においても、その有用性は従前と変わらないものと考えるところ。
戸別受信機の「地域住民・ユーザ視点」からの実感をとおして、今後とも、防災・減災に向けた住民への情報伝達に係る有用性の一助として、このような通信手段の確保が引き続き、全国的に整備、充実することを期待したい。



■参考文献:
出典[1]: 資料13-2-1 情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会報告(案)「業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条件」のうち、「60MHz帯デジタル同報系防災行政無線の低廉化」、平成26年7月3日
https://www.soumu.go.jp/main_content/000304650.pdf
出典[2]: 中国総合通信局「同報系防災無線システムの低廉化に向けた調査検討」報告書、平成26年3月、同報系防災無線システムの低廉化に向けた調査検討
出典[3]: 例えば、独立行政法人情報通信研究機構(NICT)および次世代安心・安全ICTフォーラム
お知らせ&イベント | 災害対策技術講演会2014 | NICT-情報通信研究機構
加藤 数衞 – 災害対策技術講演会2014 (2014年6月18日開催)
出典[4]: 住民への災害情報伝達手段 | 住民への災害情報伝達手段 | 総務省消防庁 (令和7年3月改定)
追伸:【季節の光景】
例年になく連日、猛暑日が続き、今後、水不足も懸念されている。東日本は7月上旬の梅雨明け予想が伝えられる中、自宅軒下の葡萄棚が厳しい陽射しを和らげてくれている。
毎年、旧盆の頃には、濃い紫色に甘熟するが、今夏は、この気候で早まるかも知れない・・・。